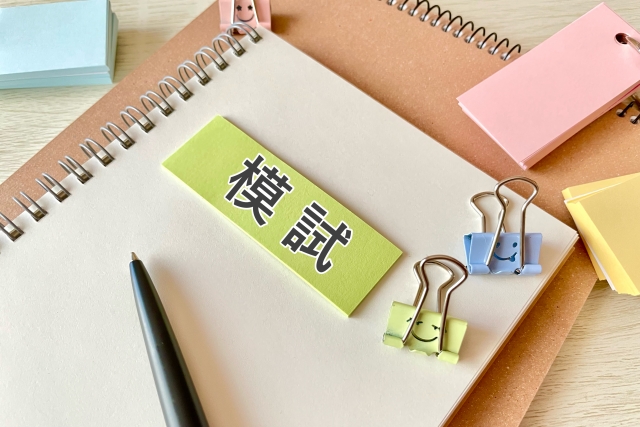こんにちは。
今回は受験生あるあるだと思いますが、模擬試験で思うような点数が取れなかったときや、そんな時にSNSで見かける高得点を取っている他人と比べてしまう件について記事を書いてみます。
模擬試験の結果って気になりますよね。メンタルが豆腐の僕はSNSで高得点のポストを見ては自分の不甲斐なさに落ち込んでました。
人の心理として、どうしても隣の芝が青く見えてしまうことはあると思うんですよね。まして本当に隣の芝が青いのであれば、羨ましく思うのは当然だと思います。その点はごくごく普通のことだと思います。
そこで!そもそも模擬試験って、どういう位置づけなのかを改めて再認識した方が良いと思うんです。模擬試験は文字通り「本番を想定したもの」なので練習なんですよ。
これが軸なんですが、考え方によっては「本番を想定しているなら本番もダメだ」であったり、「良い結果は出せなかったけど、これが本番じゃなくてよかった」となる。当然ながら後者の方がプラス思考で好ましい捉え方でしょう。
しかも多くの人が模擬試験は複数回受験するので、その都度浮き沈みするのはナンセンスです。
…とは言え、一喜一憂しますよね!笑
やっぱり点数が良いにこしたことないし、次への弾みになるし、今までの勉強方法で大丈夫なんだなって再認識することだってできます。その心理、痛いほど理解できます。
模試の本当の目的
・現時点での「弱点」を発見するため
・試験本番の「時間感覚」を掴むため
・メンタルコントロールの練習にもなる
模擬試験の目的って、現時点の自分の弱点を見つけたり、時間配分や、問題を解く順番を色々と試してみる機会なんですよね。模擬試験は毎回高得点を出したって、本試験でとれるかどうかなんて確約はないわけで(可能性は高いでしょうけど)結局のところダメだった方が今後の勉強方法や自分にとっての弱点を把握することができるのがメリットでもあります。
僕自身もそうでしたが、仮に得点できたとしても「多分これじゃないかな…」というあやふやな知識で正解した問題は嬉しくありませんでした。最初のころはそういった問題を解くときに何かしらの印もつけていなかったので、あとから自己採点しても、どの問題があやふやな知識で解答したのかわからなかったんです。
ですから模擬試験も何回か受ける中で「この問題は自信がないぞ」と思う問題には三角やはてなマークをつけて後からの見直しに役立てていました。
だから結果がよくなくても本来は一喜一憂するのではなく、「今回はどこがダメだったのかな。見直すべき論点はどこなんだろう。問題を解く順番を次回は変えてみようかな」と考えることが大事であって、落ち込んでる時間が勿体ないんです。
ちなみに僕の場合は問題を解く順番を複数回試してみました。その結果、次の通りの順番で解くのが自分にとってのベストだと結論を出しました。
「文章理解→記述をぱらっと見る→憲法→民法→行政法→多肢選択→基礎知識」
文章理解は苦手だったので、長文を読むだけの元気がある最初に持ってきてじっくり理解して確実に正答できるように努めました。
最初は模擬試験にすらすごい緊張して受験後はぐったり、自己採点もせず結果が公表されるまで放置ということもありましたが(これは最悪ですね。。)
色々試そうと思いはじめてからは模擬試験を受けた後は、コーヒーで一息ついてから早々に自己採点して、受験中にチェックしたあやふやな知識で回答した個所や自信あったのに間違えた問題などを解説講義で確認するようにしました。基本的には受験後3日以内、早い時はその日のうちに自己採点を行って解説講義から復習まで終えて、弱点とわかった論点をテキストや問題集などを見返すようにしました。
模擬試験はしょせん模擬試験です。そうでも思わないとやってられなかったです。
SNSの高得点報告に心が揺れる時
そんな時、SNSで高得点の報告を目にしたら心穏やかにいられませんよね。「いいな。すごいな。S判定なんて取ったことない…。自分は下から数えたほうが早いくらいなのに、こんな上位得点なんてすごいな」って思いました。
僕が初めて受けた模擬試験の結果を覚えていますが、散々たる結果で2000人ぐらいの受験者のうち、下から50番目ぐらいでした。勿論ほぼすべてD判定。AやSなんてかすりもしませんでした。
もうね…言葉が出ないとはこのことですよ笑
SNSに結果をアップする人は、ほとんどの人が高得点を取った人なんです。点数が悪かった人も中にはいますが、ほとんどが高得点の人。ましてそのどちらでもない中ぐらいの人の得点なんてほとんど誰も公開しません。だから、いちいち気にしてはいけないんですけど、やっぱり気になりますよね笑
気になるが故に、僕自身導き出した結論として、模擬試験シーズンの間はSNSをきっぱりやめました。もうアプリをアンインストールしたんです。そうしたら絶対見ることはないので。
すると他人の結果に心揺さぶられることもなく、また勉強中も都度SNSを見る時間がなくなるので勉強時間が増えたり集中できるようになったので、良いことがたくさんありました。
他人が気になるようならSNSを削除してしまう。これが一番効く薬です。
まとめ】模試は「道しるべ」であって「合否」ではない
模試の点数=合格の可能性、ではない
模試後の「行動」が一番の鍵
焦らず、冷静に、自分のペースで積み重ねていきましょう。
模擬試験はしょせん模擬試験です。合格を保証するものではないので、自分の弱点を見つけたり、時間配分や解く順番を試す場として割り切りましょう。
明らかにわからなかった問題や勘で正解してしまった問題は、苦手論点と思えるので、それらを見つけて確実に復習段階で潰していく。 苦手論点が模擬試験に出てくるのって意外とラッキーだと思うんですよね。僕の場合、苦手論点が出ると「あー、やっぱり出てきたし不正解だった。苦手だから理解も乏しかったし正解できなかったのは当たり前だよな。やっぱりきちんと理解して進まないとダメだな」って前向きに捉えるようにしました。
「この苦手論点は本試験でも出ませんように…」とお祈りしても、それは神のみぞ知ることであって、もし出題された場合は「ちゃんと勉強しておけばよかった」と後悔するのが関の山です。模擬試験で自分の苦手論点が出た時はラッキーなんです。
比べるのは過去に受験した自分であって、見たことも会ったこともないSNSの他人の報告に一喜一憂するのは得策ではありません。焦ることなく、目の前にある課題や問題をたんたんとこなしていく。これに尽きます。周りに振り回されることなく冷静に自分の道を進んで勉強頑張ってくださいね。
今回も最後までお読み頂きましてありがとうございました。