遺言、相続、後見人等
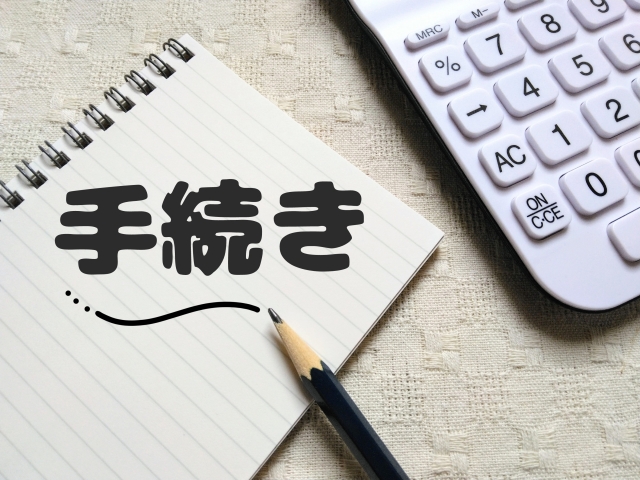
昨今は遺言を残す方が多くなってきましたが、それでも実際遺言書を作成するのは全体の10%に満たない状態です。
遺言書を作成するきっかけは、「自身が高齢になってきたから」が最も割合として高いですが、若くても不慮の事故や思いがけないことにより意思疎通が困難な状態になる可能性もあります。
そんな万一の時に「相続トラブルにならないように」と最後の思いやりをもって作成するのが遺言書とも言えるのではないでしょうか。
「遺せる資産なんてうちにはないから」と、ご謙遜される方もおられるかもしれませんが、普段生活を営んでおられたら少なからず遺された親族に渡るものが必ず発生します(思い出の詰まった振袖など)
もし明確な意思表がされない状態で突然の事態に陥った時、遺言書がなければ「負債があるかもしれないし、よくわからないから」といった理由でご遺族が相続放棄をしてしまう可能性があります。
そうなれば、大切な思い出も全て放棄されてしまいます。
そうならない為にも、しっかりと遺言書を作成しておくことで、普段の生活も安心して過ごすことができるようになるのではないでしょうか。
遺言と相続はセットに扱われることが多いです。というよりセットにすべきと私も思います。
なぜか?
それは「相続」を「争続」としてしまわないようにするために予め遺言を残しておく為です。
遺言できちんと財産分与を決めておく、さらに遺言には付言(ふげん)という思いを書き足すことが出来ます。例えば「〇〇には現金は少ないけど不動産をあげるね」「今までありがとう」など。
遺言として最期のお手紙をもらった遺族はきっと和やかな気持ちでその後の人生を歩んでくれるじゃないでしょうか。
遺言作成から、その後の相続は勿論。
後見制度についても承っておりますので、色々と安心して生活できるよう沢山お話しながら進めて参りましょう。
【お問合せの流れ】
1.メールもしくはお電話にてご相談ください。
2.詳細をお聞かせください。いろいろお話ししましょう。
(基本的にはご訪問させて頂きますが、リモートでも対応させて頂きます)
3.内容をお聞かせ頂き、受任(着手金の受領等)・業務の開始
※場合によっては、信頼できる他士業の先生をご紹介させて頂きます。
4.完了(残額の受領)



